1. 導入—今日の通読での素朴な疑問
今朝の通読で創世記22章を読みながら、私はある疑問に立ち止まりました。アブラハムの信仰は本当に「人間離れ」していたのだろうか?神様は一人子イサクを捧げよと命じられ、アブラハムは黙って従った。この沈黙の中に、いったい何があったのでしょうか。
同時に、サムエル記での契約の箱の帰還のストーリーも心に響きました。ベテ・シェメシュの人々が箱をのぞき見て打たれた出来事と、アブラハムの物語の間には、ある共通点があるように感じたのです。
それは「三日目」という時間軸と、「主の山には備えがある」という信仰の核心です。
2. モリヤの山はどこ?アブラハムの三日間の旅
創世記22:2-4
「あなたの愛しているひとり子イサクを連れてモリヤの地に行き、わたしが示す山で彼を全焼のささげ物として献げなさい。」翌朝早く、アブラハムはろばに鞍を置き…三日目に、アブラハムは目を上げて、その場所を遠くから見た。
**モリヤの地(הָאֶרֶץ הַמֹּרִיָּה、ハー・エレツ・ハッモリヤ)**は後に神殿が建てられる場所、つまりエルサレムのことです(歴代誌下3:1)。
アブラハムが出発したのはおそらく**ベエル・シェバ(בְּאֵר שֶׁבַע)**のあたりで、そこからエルサレムまでは約80-90km。三日間の旅は、ただ距離を移動するだけではありませんでした。これは神様が意図的に設けられた「待ち時間」だったのです。
なぜ三日間だったのか?
この三日間、アブラハムは何を考えていたのでしょう。息子イサクと並んで歩きながら、毎晩キャンプを張りながら、彼の心の中では激しい葛藤があったはずです。
しかしヘブル人への手紙は、驚くべき事実を明かします。
3. イサクは何歳だった?沈黙が語るもの
聖書はイサクの正確な年齢を記していませんが、いくつかのヒントがあります:
- **「若者(נַעַר、ナアル)」**と呼ばれている(22:5, 12)—12歳以上の少年・青年
- 自分で薪の束を背負って登った—ある程度の体力がある年齢
- 「火と刃物はどこですか?」と質問—物事を理解する知性
多くの学者は、イサクは15-25歳程度だったと推測します。つまり、彼は抵抗しようと思えばできたはずです。
イサクの沈黙は、父への信頼であり、同時に神への従順でした。これは後のキリストの従順を予表しています。
4. 「人間離れした信仰」の秘密—ヘブル11:19から
私たちはアブラハムの信仰を「人間離れした」ものと感じます。しかし、新約聖書はその秘密を明かしています:
ヘブル11:17-19
「信仰によって、アブラハムは試みを受けたときにイサクを献げました…彼は、神には人を死者の中からよみがえらせることもできると考えました。それで彼は、比喩的に言えば、イサクを死者の中から取り戻したのです。」
アブラハムが信じたのは:
- 神は約束を守る方である—「イサクにあって、あなたの子孫が起こされる」(創21:12)
- 神は死者をよみがえらせることができる—もしイサクが死んでも、神は彼を復活させる
つまり、アブラハムの信仰は「盲目的な従順」ではなく、**復活信仰(תְּחִיַּת הַמֵּתִים、テヒヤット・ハメーティーム)**に基づいていたのです!
これは「人間離れ」しているようで、実は最も理にかなった信仰でした。なぜなら:
- 神の約束は不変
- 神の言葉は実現する
- 神には不可能はない
5. 「三日目」の神学的意味—復活の型
創世記22:4
「三日目に、アブラハムは目を上げて、その場所を遠くから見た。」
この**「三日目(בַּיּוֹם הַשְּׁלִישִׁי、バヨム・ハシュリシ)」**は、聖書全体を通じて特別な意味を持ちます:
| 出来事 | 三日目の意味 |
| イサク奉献 | 「死者の中から取り戻した」(ヘブル11:19) |
| 出エジプト19章 | 三日目にシナイ山で主が降臨 |
| ヨナ | 三日三晩、大魚の腹の中(マタイ12:40) |
| イエス・キリスト | 三日目に死者の中からよみがえられた |
アブラハムにとって、三日目にモリヤの山が見えた瞬間、それは比喩的な「復活の日」でした。なぜなら、心の中ではすでにイサクを「死んだもの」として神に委ねていたからです。
そして実際に神が雄羊を備えてくださったとき、アブラハムは文字通り「死から命へ」イサクを取り戻したのです。
6. 「主の山には備えがある」の深い真理
創世記22:14
「それでアブラハムは、その場所の名をアドナイ・イルエ(יְהוָה יִרְאֶה、主は備えてくださる)と呼んだ。今日も、『主の山には備えがある』と言われている。」
この名前には二重の意味があります:
- יִרְאֶה(イルエ)—「見る」または「備える」
- 将来への預言—「主の山には備えがある」(未来形)
つまり、この出来事は:
- その場での神の備え—雄羊が茂みに備えられていた
- 将来の最終的な備え—神の小羊イエス・キリストの十字架
アブラハムは言いました:「神ご自身が、全焼のささげ物の羊を備えてくださる」(22:8)。彼は知らずして、神が御子を備えてくださることを預言していたのです。
ヨハネ1:29でバプテスマのヨハネが叫びます:
「見よ、世の罪を取り除く神の小羊。」
モリヤの山で備えられた雄羊は、カルバリの丘で備えられた神の小羊キリストの型だったのです。
7. サムエル記からの学び—聖さと親しさのバランス
今日の通読でサムエル記上6章も印象的でした。ペリシテから帰ってきた契約の箱を、ベテ・シェメシュの人々がのぞき見て、7万人が打たれた(6:19)という記述です。
契約の箱の帰還ルート
- ペリシテの五都市から
- ベテ・シェメシュ(בֵּית שֶׁמֶשׁ)—「太陽の家」の意味
- キルヤテ・エアリム(קִרְיַת יְעָרִים)—「森の町」の意味
- 20年間そこに留まる(7:2)
ベテ・シェメシュの悲劇は、神の聖さへの畏れを教えます。箱をのぞき見るという行為は、好奇心から出たものかもしれませんが、神様はご自身の聖さの基準を曲げられませんでした。
しかし同時に、この箱がアビナダブの家に20年間留まったことは、神様が人々と共におられることを望んでおられることを示しています。
アブラハムとの対比
| アブラハムのイサク奉献 | ベテ・シェメシュの人々 |
| 神の命令に従順 | 自分の好奇心に従った |
| 「主は備えてくださる」という信頼 | 神の聖さへの軽視 |
| 生命が守られた | 多くの人が打たれた |
両方の物語から学ぶのは:
- 神の親しさと聖さのバランス
- 神は私たちと親しくなりたいが、聖さは妥協されない
- 真の信頼は、神の性質を正しく理解することから生まれる
8. 新約の通読から—赦しと謝罪について
今日の新約通読箇所(マタイ5:23-24)も心に留まりました:
「祭壇に供え物を献げようとしているときに、兄弟が自分に何か恨みを抱いていることを思い出したなら、供え物はそこに、祭壇の前に残したまま、まず行って兄弟と和解しなさい。それから、来て供え物を献げなさい。」
なぜ「和解」が礼拝より先なのか?
イエス様がここで言われているのは、驚くべき優先順位です。神への礼拝よりも、人との和解が先なのです。
これは決して神への礼拝が軽んじられているのではありません。むしろ、人間関係の中に神が臨在されるという真理を示しています。
ヨハネの手紙第一4:20にこうあります:
「神を愛していると言いながら兄弟を憎んでいるなら、その人は偽り者です。目に見える兄弟を愛していない者に、目に見えない神を愛することはできません。」
謝罪と赦しと和解—三つの違い
私たちはしばしばこれらを混同しますが、聖書的には異なる概念です:
1. 謝罪(Apology, 道歉)
- ヘブライ語:סְלִיחָה(セリハ) —「許しを求める」
- 自分の非を認め、相手に伝えること
- 一方向的な行為(加害者→被害者)
2. 赦し(Forgiveness, 赦免)
- ヘブライ語:מְחִילָה(メヒラ) —「負債の解放」
- 相手の負債を免除し、心を解放すること
- 一方向的な決断(被害者→加害者)
- 相手が謝罪しなくても可能
3. 和解(Reconciliation, 和好)
- ヘブライ語:פִּיּוּס(ピユス) —「仲直り」
- ギリシャ語:καταλλαγή(カタラゲー) —「関係の回復」
- 双方向的なプロセス
- 信頼の再構築を含む
教会に必要なのは「和解の文化」
最近、ある主の器との交わりの中で、私は深く心を打たれる経験をしました。
それは些細な行き違いだったのですが、私が心配して連絡したとき、その方は:
- すぐに応答してくださり
- 丁寧に説明してくださり
- こちらの心配を理解してくださり
- 温かい言葉で励ましてくださいました
その応答の中に、私は「ああ、この方は本当に主に献身している器だ」と再認識したのです。
何が違ったのでしょうか?それは:
- 防衛的にならず、オープンに対話してくださった
- 説明責任を果たしながらも、関係を大切にされた
- 単に「問題ない」と済ませず、丁寧に心を通わせてくださった
「大丈夫です」で終わらせない勇気
日本の教会文化、特に日本人の文化では、「大丈夫です」「気にしないでください」で済ませることが美徳とされます。
しかし、聖書的な和解は違います。
マタイ18:15-17には、こうあります:
「もし、あなたの兄弟があなたに対して罪を犯したなら、行って二人だけのところで指摘しなさい。その人があなたの言うことを聞き入れるなら、あなたは自分の兄弟を得たことになります。」
ここにはプロセスがあります:
- まず一対一で話す
- それでもだめなら、一人か二人を連れて行く
- それでもだめなら、教会に告げる
これは「告発」のプロセスではありません。関係回復のプロセスなのです。
「ごめんなさい」「ありがとう」「大丈夫」が自然に飛び交う教会
私が願うのは、日本の教会がもっと率直に、もっと温かく対話できる場になることです。
- 「ごめんなさい、私の言い方が悪かったね」
- 「ありがとう、気づかせてくれて」
- 「大丈夫だよ。でもちゃんと話せてよかった」
こういう会話が自然に交わされる教会—それは形式的な礼儀正しさではなく、本当の家族のような交わりです。
アブラハムの和解の信仰
実は、アブラハムの信仰の根底にも「和解」があったのではないでしょうか。
創世記22章で、アブラハムは神の命令を聞いて:
- 怒らなかった—「なぜこんな矛盾した命令を?」
- 弁解しなかった—「でも、イサクは約束の子では?」
- 取引しなかった—「もう少し考える時間をください」
なぜなら、アブラハムは神との和解の中に生きていたからです。
彼は神を:
- 愛していた(主の友、ヤコブ2:23)
- 信頼していた(復活を信じた、ヘブル11:19)
- 従っていた(黙って三日間の旅に出た)
この「和解の関係」があったからこそ、理解できない命令にも従えたのです。
和解は「正しさ」より「関係」を優先する
注目すべきは、イエス様が「あなたが正しい場合」とは言われなかったことです。
マタイ5:23-24は言います:「兄弟が自分に何か恨みを抱いていることを思い出したなら」
つまり:
- たとえ自分が正しくても
- たとえ相手の誤解だとしても
- たとえ自分は悪くなくても
**「まず行って和解しなさい」**なのです。
これは「正義」よりも「関係」を優先する、キリストの心です。
実践的な和解のステップ
では、具体的にどうすればいいのでしょうか:
1. 自分の心をまず神の前に
- 祈りの中で、自分の感情を正直に吟味する
- 「私は傷ついた?」「私も相手を傷つけた?」
2. 相手に直接、優しく伝える
- メールでも、対面でも、電話でも
- 「○○のことで、少し気になったんだけど」
- 非難ではなく、I-message(私メッセージ)で
3. 相手の話を聞く
- 相手の視点を理解しようとする
- 「ああ、そういうつもりだったんだね」
4. 必要なら謝る、必要なら赦す
- 「ごめん、私の言い方が悪かったね」
- 「大丈夫だよ。もうこだわってないから」
5. 関係を確認する
- 「話せてよかった」
- 「これからもよろしくね」
主の器から学んだこと
冒頭で触れた、ある主の器との交わり—その方は私に、和解の美しさを身をもって示してくださいました。
それは:
- 迅速な応答—問題を放置しない
- 誠実な説明—逃げずに向き合う
- 温かい配慮—相手の気持ちを大切にする
- 前向きな締めくくり—関係を確認する
この経験を通して、私は思いました:「ああ、これが『兄弟と和解する』ということなんだ」と。
形式的な「すみません」ではなく、心からの対話。 表面的な「大丈夫です」ではなく、本当の理解。
これこそが、パウロが言った**「平和のきずなで結ばれて、御霊による一致を熱心に保ちなさい」**(エペソ4:3)の実践なのだと。
和解は弱さではなく、強さ
和解するには勇気がいります。なぜなら:
- 自分の非を認める必要があるかもしれない
- 誤解を解く努力をしなければならない
- プライドを捨てる必要がある
しかし、これは弱さではありません。最も強い信仰の表れです。
なぜなら:
- 神の前に正直であること
- 関係を正義より優先すること
- キリストの謙遜に倣うこと
これらは、最も成熟した信仰の姿だからです。
9. 結論—矛盾の中に真理が宿る
今日の通読を通じて、私は一つの真理に気づきました:
神の命令は時として矛盾して見えるが、その背後には一貫した愛と計画がある
- アブラハムには「イサクを捧げよ」と命じながら、実際には死なせなかった
- 「イサクにあって子孫が起こされる」と約束しながら、その子を要求した
- 契約の箱は「神の臨在」でありながら、軽々しく扱えば死をもたらす
これらの「矛盾」の中に、実は深い神学的真理があります:
- 神は死を通して命をもたらす—十字架と復活の原則
- 神の聖さと愛は両立する—だからこそ犠牲が必要だった
- 真の信仰は復活を見据える—現在の苦難の向こうに神の備えを見る
アブラハムの信仰が「人間離れ」していたのではなく、彼は神を本当に知っていたのです。神の性質を、神の約束を、神の力を。
そして私たちも、キリストの十字架と復活を通して、同じ神を知ることができます。
「主の山には備えがある」—これは過去の事実であり、現在の約束であり、未来の希望です。
「理解できないけど、信じる」って難しいですよね。 アブラハムが息子イサクを捧げようとした物語— この不思議な出来事から、「信仰」の本質が見えてきます。 noteの方に聖書初心者にも優しく書きました。 よろしかったらお読みください!
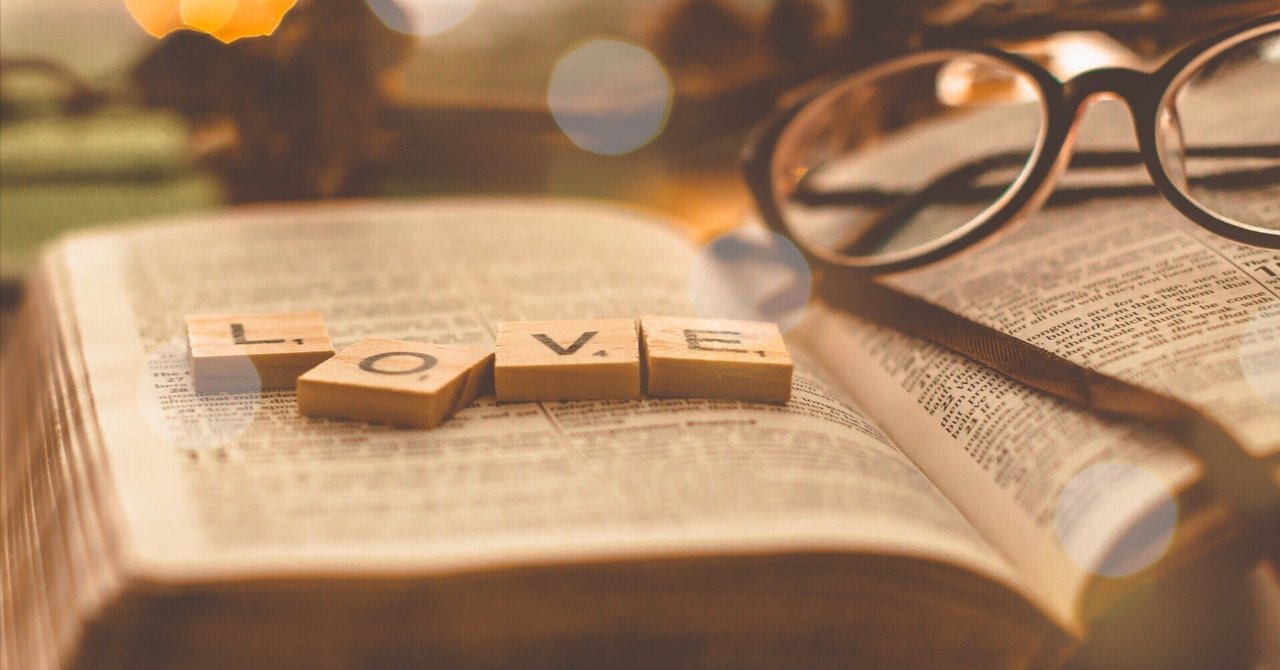
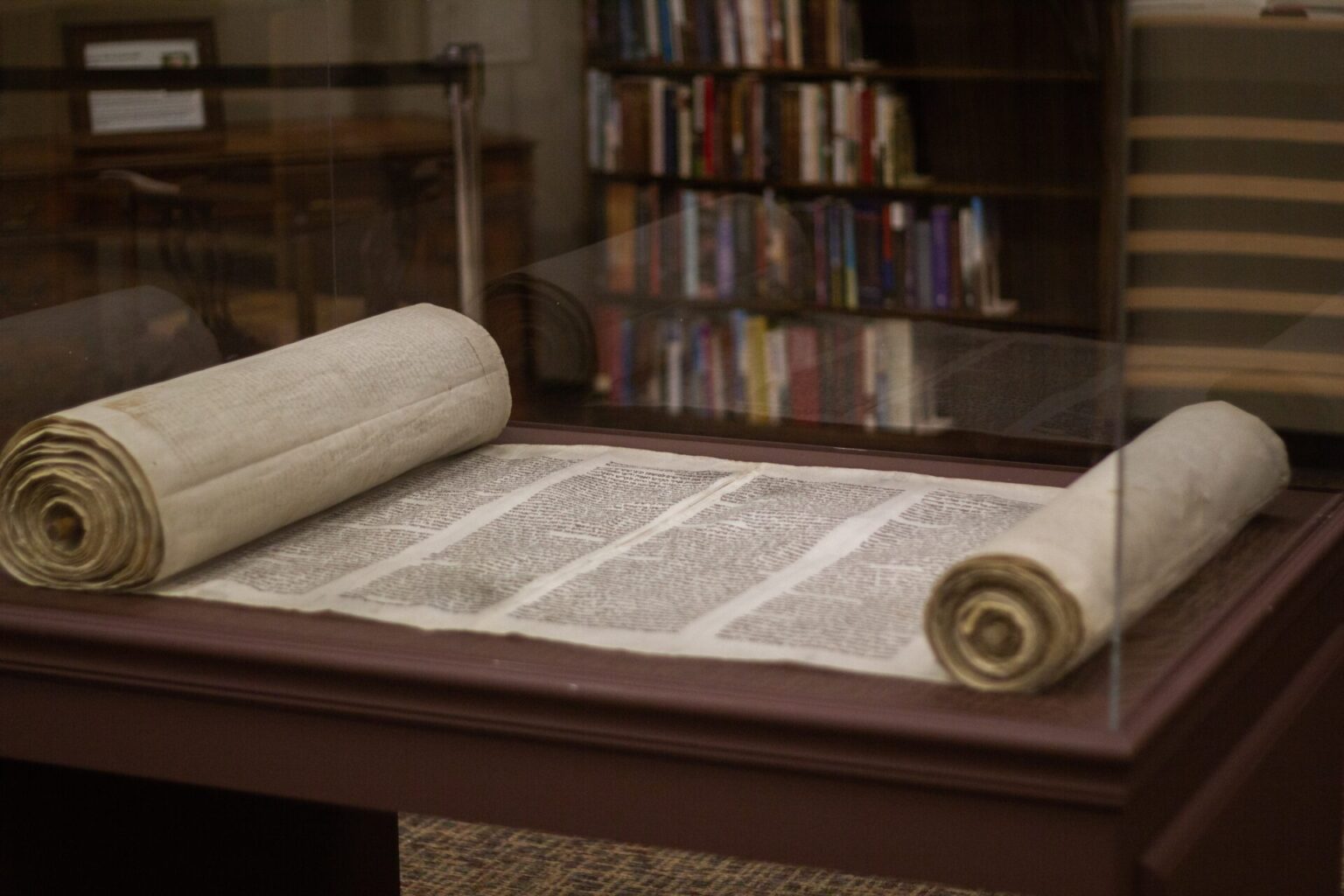
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/21be5870.7dfcaa41.21be5871.eb373a15/?me_id=1213310&item_id=19015367&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F7217%2F9784264037217.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4de23451.f5141e4f.4de23452.4ed3e44c/?me_id=1285657&item_id=13008656&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbookfan%2Fcabinet%2F01145%2Fbk4798073741.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)


コメント