はじめに
創世記24章、サムエル記第一17-18章、そしてマタイ21章。一見バラバラに見えるこれらの箇所を通読していて、一つの共通するテーマに気づきました。それは「人間の評価と神の評価の逆転」です。
普通の女性リベカが救いの歴史の重要人物となり、末っ子の羊飼いダビデがイスラエルの勇者となり、社会の最底辺にいた取税人や遊女が神の国に先に入る。そして、建築者たちが見捨てた石が、最も重要な礎の石になる。
これが、聖書が一貫して語る「神の逆転の福音」なのだと思います。
リベカの「はい、まいります」—一人の決断が歴史を動かす
創世記24章58節、リベカは家族にこう尋ねられます。「この人といっしょに行くか」。
彼女の答えは明快でした。「はい。まいります」。
ヘブライ語ではאֵלֵךְ(エーレク)。これは単なる未来形ではなく、意志を込めた決意の表現です。一度も会ったことのない人のもとへ、遠い異国へ行くという決断。家族は「しばらく、十日間ほど」と引き止めようとしましたが、リベカは迷いませんでした。
なぜ彼女はそこまで確信を持てたのでしょうか。
アブラハムのしもべの証言の中に、神の導きの明確なしるしがあったからです。しもべが祈った通りに、すべてが起こった。それを聞いたラバンとベトエルも「このことは主から出たことです」(50節)と認めざるを得ませんでした。
しかし、それでもリベカ自身の信仰による決断が必要でした。家族が決めることではなかった。「娘を呼び寄せて、娘の言うことを聞いてみましょう」(57節)。誰も代わりに決断してくれない。最終的には、自分自身で「はい」と言わなければならない瞬間がある。
そしてリベカは祝福されます(60節)。「あなたは幾千万にもふえるように。そして、あなたの子孫は敵の門を勝ち取るように」。
これは、アブラハムへの約束の継承です。一人の女性の信仰の決断が、救いの歴史を前に進めました。彼女がイサクの妻になることで、ヤコブが生まれ、イスラエル十二部族が生まれ、やがてメシアが来られる道が開かれたのです。
「生ける神の陣」とは何か—原語から見る深い意味
サムエル記第一17章に入ると、有名なダビデとゴリヤテの戦いが描かれます。
ゴリヤテの挑発を聞いたダビデは、こう言いました。「この割礼を受けていないペリシテ人は何者ですか。生ける神の陣をなぶるとは」(26節)。
この「生ける神の陣」という表現、私は以前「大リバイバルの軍団」という解釈を聞いたことがあります。それで原語を調べてみました。
ヘブライ語でמַעַרְכוֹת אֱלֹהִים חַיִּים(マアラホート・エロヒーム・ハイイーム)。
- מַעַרְכוֹת(マアラホート)= 「戦列」「陣形」「整列した軍隊」
- אֱלֹהִים חַיִּים(エロヒーム・ハイイーム)= 「生ける神」
直訳すると「生ける神の戦列」です。
ここで重要なのは「生ける」という言葉です。ヘブライ語のחַיִּים(ハイイーム)は、単に「生きている」だけでなく、「活動している」「力を発揮している」「実在する」という意味を持ちます。ペリシテ人の死んだ偶像とは対照的に、イスラエルの神は今も生きて働いておられる、という宣言なのです。
またמַעַרְכוֹת(マアラホート)は軍事用語で、整然と並んだ戦闘部隊を指します。イスラエルの軍隊は、ただの人間の集まりではなく、「生ける神が共におられる軍隊」だということです。
ダビデにとって、イスラエル軍は単なる人間の軍隊ではありませんでした。生ける神ご自身が共におられる「神の軍隊」だったのです。だからゴリヤテがそれを侮辱することは、神ご自身を侮辱することでした。
「大リバイバルの軍団」という解釈は、おそらくこの「神が共にいて力を発揮する集団」という意味から来ているのでしょう。リバイバルでは神の臨在と力が顕著に現れますから、その意味では繋がります。しかし原語の核心は、神が共にいて守り、戦ってくださる軍隊という事実そのものです。
サウルの鎧を脱いだダビデ—あなたはあなたでいい
サウルは、ダビデを励まそうとして自分の鎧をダビデに着せました。しかしダビデは「慣れていないから」と言って脱ぎました(39節)。
そして、自分の杖と石投げ、そして五つの滑らかな石を持って行きました。
ここに深い真理があります。神は、私たちを他の誰かのコピーにしようとはされません。
サウルの鎧はサウルには合っていたかもしれません。でもダビデにはダビデの戦い方がありました。ダビデは羊飼いとして、獅子や熊と戦ってきた経験がありました(34-36節)。神は、まさにその経験を通してダビデを訓練してこられたのです。
ダビデはこう告白します(37節)。「獅子や、熊の爪から私を救い出してくださった主は、あのペリシテ人の手からも私を救い出してくださいます」。
これは、過去の神の真実さが、未来の信仰の根拠になるということです。
私たちにも同じことが言えます。他の誰かの「鎧」を着る必要はありません。神は、私たち一人一人を、それぞれの経験と賜物を持った個人として訓練してこられました。あなたにはあなたにしかできない戦い方があります。あなたにしか書けない文章があります。あなたにしか伝えられない証しがあります。
ダビデが羊を守ってきた経験が、イスラエルを守る戦いに繋がったように、私たちが今まで歩んできた道、学んできたこと、苦しんできたことすべてが、今の使命に繋がっているのです。
「見捨てられた石が礎の石に」—イエスが語った逆転の真理
マタイ21章に入ると、イエスは祭司長たちとパリサイ人たちに、ぶどう園のたとえを語られます。そして、詩篇118篇を引用してこう言われました(42節)。
「家を建てる者たちの見捨てた石。それが礎の石になった。これは主のなさったことだ。私たちの目には、不思議なことである」。
この言葉の原語を見てみましょう。ヘブライ語(詩篇118:22)では:
אֶבֶן מָאֲסוּ הַבּוֹנִים הָיְתָה לְרֹאשׁ פִּנָּה(エベン・マアス・ハボーニーム・ハイェター・レロシュ・ピナー)
- אֶבֶן(エベン)= 石
- מָאֲסוּ(マアス)= 拒絶した、退けた、無価値とみなした
- הַבּוֹנִים(ハボーニーム)= 建築者たち
- רֹאשׁ פִּנָּה(ロシュ・ピナー)= 「隅の頭」= 礎石、要石(cornerstone)
この礎石/要石には二つの意味があります。一つは、建物全体の基準となる基礎の隅石。これがずれると建物全体が歪みます。もう一つは、アーチの頂点で全体の重みを支える要石です。
この言葉には、いくつもの深い意味の層があります。
第一の層—歴史的予型: イエスは当時の宗教指導者たち(「建築者たち」)によって拒絶されましたが、神はその拒絶されたイエスを、神の国という建物の最も重要な石としてお立てになりました。
第二の層—神の逆説的な働き: 人間が無価値と判断したもの、捨てたものを、神は最も重要なものとして選ばれます。これは神の国の原理そのものです。最も小さい者が最も大きく、仕える者がリーダーとなり、死によって命を得るのです。
第三の層—イスラエルの使命の転換: イエスは続けてこう言われました。「だから、わたしはあなたがたに言います。神の国はあなたがたから取り去られ、神の国の実を結ぶ国民に与えられます」(43節)。イスラエルは神の家を建てる「建築者」として選ばれていましたが、メシアを拒絶することで、その使命は実を結ぶすべての国民(ユダヤ人・異邦人を含む教会)に広がりました。
第四の層—個人的な適用: 私たち自身も、かつては神に「捨てられた」「無価値な」存在でした。しかし、キリストという礎石に接ぎ木されることで、神の家(教会)を構成する「生ける石」(Iペテロ2:5)とされているのです。
石の上に落ちる者、石が落ちる—二つの選択
イエスはさらに続けて言われました(44節)。「また、この石の上に落ちる者は、粉々に砕かれ、この石が人の上に落ちれば、その人を粉みじんに飛ばしてしまいます」。
この言葉は、ダニエル書2章の預言(ネブカデネザルの夢)を背景にしています。そこでは、一つの石が人の手によらずに切り出され、像を打ち砕き、最終的にこの石が大きな山となって全地に満ちます。
イエスは、二つの異なる状況を描いておられます。
「石の上に落ちる」とは、自分からキリストに当たること、つまりつまずきを表します。キリストにつまずく者、キリストを拒絶する者は「粉々に砕かれ」ます。ギリシャ語でσυνθλασθήσεται(シュンスラステーセタイ)= 完全に粉砕される、です。
しかし、これは必ずしも悪い砕きではありません。むしろこれは:
- プライドの砕き—自分の義を捨ててキリストに降参する
- 悔い改め—自分の罪と無力さを認める
- 良い砕き—新しい形に作り直されるための必要な過程
パウロも「この石につまずく」ことで回心しました(使徒9章)。
一方、「石が人の上に落ちる」とは、キリストによる最終的な裁きを表します。ギリシャ語でλικμήσει(リクメーセイ)= 粉みじんにする、ちりのように散らす、です。
今、へりくだってキリストにつまずく(=悔い改めて信じる)なら、砕かれても新しく造り変えられます。しかし、キリストを拒絶し続けるなら、最終的にキリスト(石)が上から落ちてきて、裁きによって完全に粉砕されます。
イエスは、パリサイ人たちを論破したのではなく、彼らの前に二つの選択肢を置かれたのです。今悔い改めるか、後で裁かれるか。
取税人と遊女が先に—正直な葛藤の価値
二人の息子のたとえ(28-32節)で、イエスはさらに鋭い真理を語られました。
兄は「行きます。お父さん」と言いましたが、行きませんでした。弟は「行きたくありません」と言いましたが、後悔して出かけて行きました。
イエスは言われます。「まことに、あなたがたに告げます。取税人や遊女たちのほうが、あなたがたより先に神の国に入っているのです」(31節)。
ギリシャ語で「悪かったと思って」はμεταμεληθείς(メタメレーテイス)= 「後で心が変わった」「悔やんだ」です。これは、正直な葛藤と悔い改めの過程を表しています。
弟は最初、正直に「行きたくない」と言いました。でも、その後、心が変わりました。そして実際に行動しました。これは完璧ではありません。でも本物です。
取税人や遊女たちは、自分の罪を知っていました。だから悔い改めることができました。一方、パリサイ人たちは、自分は正しいと思っていました。だから悔い改める必要を感じませんでした。
私も時々、自分の中にパリサイ人的な心を発見して驚きます。「私はちゃんと聖書を読んでいる」「私は神学を学んでいる」—そういう思いが、知らないうちに高慢になっていきます。
高慢との戦い—何も持っていないのに
ここで正直に告白しなければなりません。私は高慢と戦っています。
おかしなことに、「高慢になれるようなものは何も持っていない」にもかかわらず、高慢と戦っているのです。少し笑えますが、でもこれが現実です。
高慢は、何かを持っているから起こるのではありません。実は、何も持っていなくても高慢になれる。それが高慢の恐ろしさです。
アダムとエバは、禁じられた実を食べる前、何も持っていませんでした。でも「神のようになれる」という誘惑に負けました。高慢は、持っているものの量ではなく、心の姿勢なのです。
パウロはこう言っています。「私は使徒の中では最も小さい者であって、使徒と呼ばれる価値のない者です。なぜなら、私は神の教会を迫害したからです。ところが、神の恵みによって、私は今の私になりました。そして、私に対するこの神の恵みは、むだにはならず、私はほかのすべての使徒たちよりも多く働きました。しかし、それは私ではなく、私にある神の恵みです」(Iコリント15:9-10)。
パウロは最も多く働いたと認めています。でも、すぐに「しかし、それは私ではなく、私にある神の恵みです」と付け加えます。これは偽りの謙遜ではありません。パウロは実際に多く働きました。それを否定していません。でも、その源泉が神であることを知っています。
ダビデも同じでした。ゴリヤテを倒した後も、こう言いました。「この全集団も、主が剣や槍を使わずに救うことを知るであろう。この戦いは主の戦いだ」(I サムエル17:47)。
ダビデは自分の武勇を誇りませんでした。「これは主の戦いだ」と。でも同時に、ダビデは勇敢に戦いました。石を投げたのはダビデです。走って行ったのもダビデです。これが、真の謙遜と真の勇気の組み合わせです。
本当に危険な高慢は、自分が高慢であることに気づかない高慢です。パリサイ人たちは、自分が高慢であることに気づいていませんでした。彼らは本当に、自分は正しいと信じていました。
でも、もし私たちが自分の高慢に気づいて戦っているなら、それ自体が聖霊が働いておられる証拠なのです。
「神の国の実を結ぶ」とは—聖霊の働き
イエスは言われました。「神の国はあなたがたから取り去られ、神の国の実を結ぶ国民に与えられます」(43節)。
私は正直に言って、「実を結べていない」と感じることがあります。でも、ここで大切な真理を思い出す必要があります。
実を結ぶのは私たちではなく、神です。
イエスはヨハネ15章5節でこう言われました。「わたしを離れては、あなたがたは何もすることができない」。
原語で「実を結ぶ」はποιοῦντα τοὺς καρποὺς(ポイウンタ・トゥース・カルプース)= 「実を作る」「実を生み出す」です。
しかし、ガラテヤ5章22節の「御霊の実」を見てください。「御霊の実」です。つまり、聖霊が私たちのうちに結ばせてくださる実なのです。
イエスが言った「神の国の実を結ぶ国民」とは:
- 悔い改める心を持つ国民—取税人や遊女のように、自分の罪を認めて悔い改める人々
- 信仰によって応答する国民—バプテスマのヨハネを信じた人々のように、神の言葉に応答する
- 神の愛を受け取り、それを流す国民—ぶどう園の主人に忠実に仕える農夫のように
実を結んでいないのではありません。まだ成長の過程にあるのです。種が地に落ちて、芽を出して、成長して、やがて実を結ぶ—その過程のただ中にいるのです。
イエスは言われました。「一粒の麦がもし地に落ちて死ななければ、それは一つのままです。しかし、もし死ねば、豊かな実を結びます」(ヨハネ12:24)。
おわりに—主があなたを祝福し
今日の三つの箇所には、一つの共通テーマがありました。
人間の評価と神の評価の逆転。
- リベカ: 普通の女性だったが、神は彼女を選んで救いの歴史の重要人物にされた
- ダビデ: 末っ子の羊飼いだったが、神は彼をイスラエルの勇者にされた
- 取税人や遊女: 社会の最底辺だったが、神の国に先に入った
そして、見捨てられた石が礎の石になった。
これが福音の逆説です。神は、世が無価値とみなすものを選び、世が強いとみなすものを恥じ入らせます(Iコリント1:27-28)。
だから、自分が「実を結べていない」と感じる時こそ、神が働こうとしておられる時かもしれません。
完璧でなくても、本物でいい。
正直に葛藤しながら、でも悔い改めて、神の前に出続ける。それが、取税人が義と認められた道です。
最後に、民数記6章のアロン的祝祷をもって、この記事を締めくくりたいと思います。
主があなたを祝福し、あなたを守られますように。 主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。 主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
ダビデがゴリヤテに向かって行った時、主は御顔をダビデに向けておられました。だからダビデは恐れませんでした。
あなたが今日、聖書を読み、神を求め、人々に仕える時、主は御顔をあなたに向けておられます。
見捨てられた石が礎の石となる福音。 取税人や遊女が先に神の国に入る福音。 末っ子の羊飼いがイスラエルの勇者となる福音。 何も持っていない者が、神の恵みによって豊かに用いられる福音。
この逆転の福音を信じて、今日も、明日も、歩み続けましょう。
アーメン。

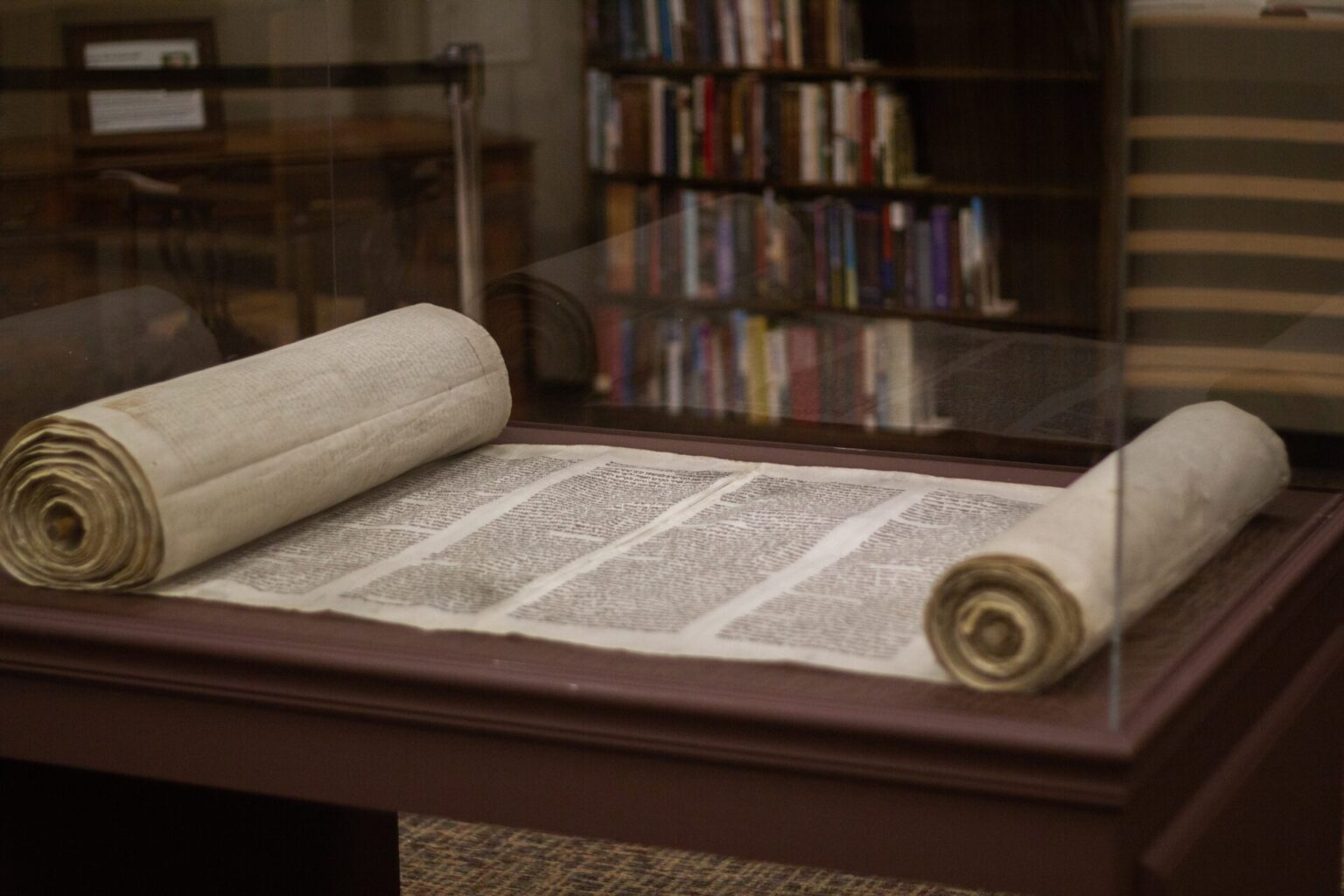

コメント