通読箇所:創世記18:1-15、士師記19-20章、マタイ14章
はじめに
今日の通読は、人間の信仰と不信仰、残酷さと憐れみ、絶望と希望が交錯する箇所でした。
- 創世記18章:サラの不信仰の笑いと、「主に不可能なことがあろうか」という問いかけ
- 士師記19-20章:聖書の中で最も心が痛む、イスラエルの堕落の記録
- マタイ14章:バプテスマのヨハネの殉教と、五千人の給食、ペテロの水上歩行
正直に言うと、士師記19-21章は私が最も嫌いな箇所でした。でも、Claude先生との対話を通して、神様がこの暗闇の中にも光を置いてくださっていることを発見しました。
実は、私はこの箇所から人生を変えるレーマ(神の語りかけ)を受け取ったことがあります。複雑な思いを抱えていましたが、今日の学びを通して、神様の深い憐れみと贖いの御業を見ることができました。
Part 1:今日の通読箇所 – 簡潔なまとめ
創世記18:1-15「サラの笑い – 主に不可能はない」
友喜:創世記18章で、サラが「老いぼれてしまったこの私に、何の楽しみがあろう」と心の中で笑いましたよね(18:12)。でも神様は「サラはなぜ笑うのか。主に不可能なことがあろうか」と言われました(18:13-14)。
Claude先生:この箇所は信仰についての深い教えです。ヘブル語で「主に不可能なことがあろうか」は「הֲיִפָּלֵא מֵיְהוָה דָּבָר(ha-yippaleh me-YHWH davar)」、直訳すると「主から何かが不思議すぎる(impossible)だろうか?」という修辞疑問文で、答えは「ノー!」です。
興味深いのは、「イサク(יִצְחָק Yitzchak)」という名前自体が「彼は笑う」という意味だということです。神は、サラの不信仰の笑いを、喜びの笑いに変えてくださいました(21:6)。
友喜:わざわざこのエピソードが書いてあるのは、「不信仰にならないで、信じなさい」と言われている気がします。
Claude先生:その通りです。私たちも疑い、笑い、恐れます。でも神はその弱さを知りながら、約束を成就されます。これが今日の他の箇所、特にマタイ14章のペテロの水上歩行ともつながってきます。
マタイ14章「人間の残酷さと、イエスの憐れみ」
友喜:マタイ14章も辛い箇所から始まりますね。バプテスマのヨハネが、ヘロデヤの娘の踊りのせいで首をはねられる(14:6-11)。人間の残酷さに心が痛みます。
Claude先生:ヘロデは「心を痛めた」(14:9)のに、自分の誓いと面子のために義人を殺しました。これも士師記の「めいめいが自分の目に正しいと見えることを行う」状態です。
でも、その直後のイエスの反応を見てください:
14:13「イエスはこのことを聞かれると、舟でそこを去り、自分だけで寂しい所に行かれた」
イエスも悲しまれたのです。でも群衆を見て深くあわれみ、癒されました(14:14)。
友喜:五つのパンと二匹の魚の奇跡ですね(14:17)。ゲマトリア的に何か意味があった気がして…
Claude先生:ヘブル語/ギリシャ語でのゲマトリア的意味は定かではありませんが、数字の象徴性として:
- 5 = 恵み(トーラーは5書、人間の指は5本)
- 2 = 証し、契約(申命記では2人の証人が必要)
- 12のかご = イスラエルの12部族、完全な満たし
つまり、神の恵み(5)と証し(2)から、イスラエル全体(12)への完全な供給が生まれるという構図です。
友喜:そして14章30-31節、ペテロが「風を見て、こわくなり」沈みかけた時、イエスはすぐに手を伸ばされました。「信仰の薄い人だな。なぜ疑うのか」と。
Claude先生:注目すべきは、イエスが**「すぐに」**手を伸ばされたことです。叱責の前に救助です。「信仰の薄い人だな」という言葉も、見捨てる言葉ではなく、「もっとわたしを信頼できるのに」という愛の嘆きです。
友喜:世の波風に目を留めるのではなく、ただ主イエスの御言葉に目を留めることができますように…これはサラの不信仰とも、今から学ぶ士師記の混乱ともつながりますね。
Claude先生:素晴らしい洞察です!そして14章36節:「さわった人々はみな、いやされた」。**「みな」**です。選択的ではなく、全員。これがメシアの王国の到来のしるしでした(イザヤ35:5-6)。
今日、すべての人が即座に癒されるわけではないのは、まだ王国が完全には来ていないからです。でも、やがて来る王国では、すべての涙がぬぐわれます(黙示録21:4)。
これらの箇所を心に留めて、今から士師記19-21章の深い学びに入っていきます。
Part 2:士師記19-21章 – 深い対話考察
対話1:レビ人の正体 – なぜ祭司が妾を持つのか?
友喜:Claude先生、士師記19章を読んで本当に胸が悪くなりました。このレビ人は祭司なのに、なぜ妾を持っているんですか?しかも、自分が襲われそうになると妾を差し出して、彼女を守ろうともしない。最悪の男です。
Claude先生:友喜、その怒りは正しい反応です。でも、まず一つ確認させてください。すべてのレビ人が祭司ではありません。
- 祭司(コヘン):アロンの子孫のみ。神殿で犠牲をささげる
- レビ人:レビ族全体。祭司を補助し、教える役割
でも、それでも彼は神に仕える者です。だからこそ、彼の行動は許しがたいのです。
友喜:なるほど。でも、どちらにしても神に仕える立場ですよね。妾を持つこと自体が問題だと思います。
Claude先生:その通りです。当時の文化では妾を持つこと自体は違法ではありませんでしたが、創世記2章の一夫一婦の理想からは遠く離れています。さらに重要な点があります。
19章2節で「そのそばめは彼をきらって、彼のところを去り」とありますが、実はヘブル語原文では「וַתִּזְנֶה עָלָיו(vatizne alav)」、つまり「彼に対して姦淫した」という動詞が使われています。
友喜:え!?新改訳では「きらって」となっていますが、原語は「姦淫した」なんですね。それで彼女は父の家に逃げ帰ったと。
Claude先生:そうです。つまり、この関係は最初から破綻していた可能性があります。でも興味深いのは19章3節です:
「彼が目を上げて見ると、三人の人が彼に向かって立っていた。彼は、見るなり、彼らを迎えるために天幕の入口から走って行き、地にひれ伏して礼をした」
ヘブル語は「לְדַבֵּר עַל־לִבָּהּ(ledabber al-libbah)」= 「彼女の心に語りかける」。これは実は、ホセア書2章14節で神がイスラエルに対して用いる表現と同じです。
友喜:ということは、この時点では彼はまだ悔い改めて、妾を取り戻そうとする「善意」があったということですか?
Claude先生:そう見えます。彼女の父も彼を歓迎します(19:4-9)。でも、ギブアでの出来事で、彼の本性が露わになります。19章25節:
「しかし、人々は彼に聞こうとしなかった。そこで、その人は自分のそばめをつかんで、外の彼らのところへ出した」
彼は自分を守るために、彼女を犠牲にしました。
対話2:創世記19章との恐るべき対比
友喜:この箇所を読んでいると、創世記のソドムとゴモラの話を思い出すんですが…
Claude先生:その通りです!友喜、素晴らしい洞察です。士師記19章は、意図的に創世記19章(ソドムの滅び)を模倣しています。見比べてみましょう:
| 創世記19章(ソドム) | 士師記19章(ギブア) |
| 二人の御使いが町に来る | レビ人と妾が町に来る |
| ロトが客人をもてなす | 老人が客人をもてなす |
| 町の男たちが「あの男たちを知りたい」と要求 | 町の男たちが「あの男を知りたい」と要求 |
| ロトが娘たちを差し出そうとする | 老人が娘と妾を差し出そうとする |
| 御使いが介入し、ロトと家族を救う | 誰も介入せず、妾は死ぬ |
| 神がソドムを滅ぼす | イスラエルがギブアを滅ぼす |
友喜:決定的な違いは、創世記では神が介入しましたが、士師記では神の臨在がほとんど感じられないことですね…
Claude先生:その通りです。これは、イスラエルがソドムと同じレベルまで堕落したことを示しています。エゼキエル書16章49-50節でも、神はエルサレムをソドムと比較して裁かれます。
「王がいない」時代の恐ろしさがここにあります。
対話3:名前のない女性 – 神は覚えておられる
友喜:この妾の女性には名前すらありません。彼女が受けた不正義を思うと、本当に心が痛みます。なぜ神様はこんなひどい話を聖書に記録されたんでしょうか?
Claude先生:友喜、それは本当に重要な質問です。この女性が受けた不正義を数えてみましょう:
- 妾として扱われる(完全な結婚の権利なし)
- レビ人に見捨てられる(19:25)
- 一晩中犯され続ける
- 死にかけて戻ってくるが、夫は「立ちなさい。行こう」としか言わない(19:28)
- 死体を12に切り分けられる
19章28節の冷酷さ:「立ちなさい。行こう」と言ったが、何の返事もなかった。彼は彼女の安否を気遣いません。彼女は物として扱われています。
友喜:読むだけで涙が出ます。でも、なぜ神様はこれを記録されたのですか?
Claude先生:私は、神がこの無名の女性の苦しみを記録されたということ自体が、神の性質を表していると思います。
- イスラエルは彼女を忘れるかもしれない
- レビ人は彼女を物として扱った
- でも神は彼女の苦しみを聖書に記録し、永遠に覚えておられる
詩篇56篇8節:「あなたは私のさすらいをしるしておられます。私の涙をあなたの皮袋にたくわえてください。それは、あなたの書に記されているではありませんか」
神は見ておられます。そして記録しておられます。
友喜:…ありがとうございます。その視点で読むと、この箇所が少し違って見えてきます。
対話4:なぜ最初イスラエルが負けるのか?
友喜:士師記20章で、ベニヤミン族は明らかに罪を犯しているのに、最初の2回の戦いでイスラエルが負けますよね。これはどうしてですか?罪を犯したのはベニヤミンなのに…
Claude先生:素晴らしい疑問です!20章18節を見てみましょう:「イスラエル人は立ち上がって、ベテルに上り、神に伺って言った」
一見、彼らは正しいことをしているように見えます。神に伺っています。でも注目すべきは、段階的に彼らの祈りが深くなっていることです:
- 最初:「誰が最初に行くか?」(20:18)- 戦術的な質問だけ
- 二度目:「再び戦うべきか?」(20:23)- でもまだ断食なし
- 三度目:断食、いけにえ、真剣な悔い改め(20:26)
友喜:つまり、彼らも罪から完全に自由ではなかったということですか?
Claude先生:その通りです。彼らは義憤に駆られていましたが、自分たちの霊的状態を省みていませんでした。考えてみてください:
- 彼らも「王がいない」混乱の時代の一部
- レビ人の証言を鵜呑みにした(20:4-7、彼は自分が妾を差し出したことには触れていません)
- 義憤が復讐心に変わった可能性
神は、彼らが真に謙遜になるまで、勝利を与えられませんでした。
友喜:なるほど…自分も裁く心を持っていたので、これは私にとっても教訓です。
対話5:ベツレヘムの地理 – ユダ族の領地
友喜:ところで、ベツレヘムはベニヤミン族の中にあったのですか?
Claude先生:いいえ、ベツレヘムはベニヤミン族の領地ではなく、ユダ族の領地です。これが非常に重要なポイントになります。
地理的な位置関係を見てみましょう:
北:ギブア(ベニヤミン族)- 暗闇の場所、妾が死んだ場所
↓ 約5km
中:エルサレム(エブス人)- まだ征服されていない異邦人の町
↓ 約8-10km
南:ベツレヘム(ユダ族)- 妾の出身地
士師記19章の旅路は北上していました:
- ユダのベツレヘムを出発(19:1-2)
- エルサレム(エブス)を通過(19:10)
- ベニヤミンのギブアに到着(19:14)
友喜:なるほど!ベツレヘムはユダ族の領地で、妾はそこから来たんですね。
対話6:ルツ記との驚くべき対比
Claude先生:友喜、ここからが本当に興味深いところです。ルツ記1章1節を見てください:
「士師たちが治めていたころのこと」
ルツ記は士師記と同じ時代設定です!同じ混沌の時代に、全く違う物語が展開されているんです。
友喜:えっ!?同じ時代なんですか!?
Claude先生:そうです。対比を見てみましょう:
| 士師記19章 | ルツ記 |
| 同じ時代、同じ混乱期 | 同じ時代、同じ混乱期 |
| ベツレヘムから来た女性 | ベツレヘムに来た女性 |
| レビ人(宗教的立場あり) | ボアズ(誠実なユダ族の男性) |
| 妾として不完全な関係 | 合法的な結婚による贖い |
| 男が女を守らない | 男が女を守り、贖う |
| 女は名前なし | 女の名前:ルツ(意味:友、仲間) |
| 死と分裂をもたらす | いのちと統一をもたらす |
| イスラエルの最悪の時 | ダビデ王家の始まり |
友喜:すごい対比ですね!同じ時代、同じベツレヘムが関係しているのに、こんなに違う…
Claude先生:そしてもっと驚くことがあります。ルツ記4章17節:
「このオベデにエッサイが生まれ、エッサイにダビデが生まれた」
ルツとボアズの子孫がダビデ王です。そして、ダビデはどこで生まれましたか?
友喜:ベツレヘムです!(サムエル記第一17:12)
Claude先生:その通り!そして、イエス・キリストもどこで生まれましたか?
友喜:ベツレヘムです!(マタイ2章)
対話7:ベツレヘムの意味 – パンの家
Claude先生:「ベツレヘム」のヘブル語の意味を見てみましょう:
ベツレヘム = בֵּית לֶחֶם(ベート・レヘム)
- בֵּית(bayit)= 家
- לֶחֶם(lechem)= パン
つまり、「パンの家」という意味です。
友喜:パンの家…
Claude先生:対比を見てください:
- 士師記19-21章:霊的な飢饉、パンの家から来た女性が死ぬ
- ルツ記:物理的な飢饉があった(1:1)が、パンの家(ベツレヘム)に戻ると祝福がある
- サムエル記:パンの家(ベツレヘム)からダビデ王が出る
- 福音書:パンの家(ベツレヘム)から真のパンであるイエスが生まれる
ヨハネ6章35節:「わたしがいのちのパンです」
友喜:ベツレヘムは、一貫して「神の供給と救い」の象徴なんですね…
対話8:ベニヤミン族の回復 – パウロへの道
友喜:ところで、パウロはベニヤミン族の出身ですよね(ピリピ3:5)。ということは、ベニヤミン族は絶滅せずに残ったということですか?
Claude先生:素晴らしい質問です!士師記21章で600人の男性が生き残り(20:47)、妻を得ます。そこから段階的な回復があります:
- 士師記21章:600人の男性が生き残り、妻を得る
- サムエル記:ベニヤミン族から最初の王サウルが出る
- 分裂後:ベニヤミンはユダと共に南王国に残る
- 捕囚後:帰還者の中にベニヤミン族がいる
- 新約時代:パウロがベニヤミン族出身と誇りを持って宣言
興味深いのは:
- サウル王(שָׁאוּל Shaul)= 最初の王、でも高慢で神に退けられた
- パウロ(元の名前:サウロ)= 同じ名前、同じ部族、でも謙遜にキリストに仕えた
友喜:神様は最も堕落した部族から、最も偉大な使徒を起こされたんですね。これが福音ですね…
Claude先生:その通りです。これが贖いです。
対話9:19章20節のレーマ – 私の証し
友喜:実は、告白があります。私はこの士師記19章が聖書の中で一番嫌いな箇所でした。でも、職安に通っていた時、19章20節の御言葉がレーマとして与えられたんです。
「安心なさい。ただ、足りないものはみな、私に任せて。ただ広場では夜を過ごさないでください」
この言葉を確信をもって受け取って就職面接を受け、一発で合格しました。その後大変なことはありましたが、今に至るまで守られています。
でも…この箇所が士師記19章だとわかって、正直がっかりしたんです。なんでこんな最悪の箇所から神様は語られたんだろうって。
Claude先生:友喜、それは本当に深い証しですね。でも、今日の学びを通して、新しい視点が見えてきませんか?
まず、この言葉を語った老人を見てみましょう(19:16-20):
- 彼はエフライム出身で、ギブアに滞在していた異邦人のような存在
- 彼だけが、放置されている旅人を見て憐れんだ
- 彼は創世記18章のアブラハムのもてなしの伝統を守った唯一の人
19:20のヘブル語: 「שָׁלוֹם לְךָ(shalom lecha)= あなたに平安を。ただ、足りないものはみな、私に任せて。ただ広場では夜を過ごさないでください」
この「広場では夜を過ごさないで」という警告は、彼がこの町の危険性を知っていたことを示しています。彼は本当に客人を守ろうとしました。
友喜:確かに…この老人は、この暗闇の物語の中の一筋の光ですね。
Claude先生:そうです。そして、この言葉は実は、ルツ記でボアズが言うべきだった言葉の先取りでもあります。
ルツ記2章8-9節、ボアズはルツに言いました: 「娘さん。よく聞きなさい。ほかの畑に拾いに行ってはいけません…若い者たちに、あなたのじゃまをしてはいけないと、私は命じておきました」
これが本来の「パンの家(ベツレヘム)」の姿です。
友喜:ということは、神様は19章20節を通して、私にルツ記のような保護と供給を約束してくださったということですか?
Claude先生:私はそう思います。神が友喜に19章20節を語られた時、神は言っておられたのではないでしょうか:
「安心しなさい(平安を)。足りないものは私が満たす。でも、危険な場所(広場)にとどまってはいけない。私の保護の中に入りなさい。」
そして友喜は:
- 確信を持って就職面接に臨んだ
- 一発で合格した
- 大変なことはあっても、守られてきた
これは、暗闇の物語の中の光の約束でした。
友喜:今、本当に感謝な思いになりました。神様は最悪の箇所からでも、贖って用いてくださるんですね。
Claude先生:その通りです。これはパウロがベニヤミン族から出たことと同じです。神は:
- 暗闇の中にも、光を置かれる
- 最も暗い箇所をも贖われる
- 「私に任せて」という約束を守られる
- 危険から保護してくださる
士師記19章は全体としては暗闇ですが、神は19章20節の一筋の光を通して友喜に語られました。これは:
- ルツ記のボアズの精神
- やがて来られるイエス(真のパン、ベツレヘムから)の先取り
- 最悪の箇所からも、神は贖って用いられるという証し
まとめ:暗闇の中の希望
私たちが学んだこと
- 人間の堕落の深さ:神なしでは、神の民ですら、ソドム以下になり得る
- 神は見捨てられた者を覚えておられる:名前もない妾の苦しみを、神は永遠に記録された
- 裁きの目的は滅ぼすことではなく、回復すること:ベニヤミン族はやがてパウロを生み出す
- 最も暗い箇所からも、神は語られる:私の19:20のレーマが証し
- ベツレヘム(パンの家)は、一貫して神の供給と救いの象徴
地理的・神学的構造
北:ギブア(ベニヤミン族)
↓
暗闇、死、分裂
↓
中:エルサレム(まだ征服されていない)
↓
将来の神の都
↓
南:ベツレヘム(ユダ族)
↓
光、いのち、統一
ダビデの出身地
イエスの誕生地
「パンの家」
時代を超えた希望
- 士師記19-21章:王なき時代の最悪の状態
- ルツ記:同じ時代、神に信頼する者への祝福
- サムエル記:ベツレヘムからダビデ王
- 福音書:ベツレヘムから王の王イエス
士師記21章25節:「そのころ、イスラエルには王がなかった。めいめいが自分の目に正しいと見えることを行っていた」
でも、やがて真の王が来られます。ベツレヘム(パンの家)から。
最後に – 読者の皆さんへ
士師記19-21章は、読むのが辛い箇所です。でも、この箇所を読んで心が痛むなら、それはあなたの心が神の心に近いということです。
神はこの暗闇を記録されました。なぜなら:
- 罪の深刻さを示すため
- 神なしでは生きられないことを示すため
- でも、その中にも神は光を置かれることを示すため
ベツレヘム(パンの家)は、常に希望の象徴です。
あなたの人生にも、「士師記19章」のような暗い時があるかもしれません。でも、神は暗闇の中にも「19章20節」のような光を置いてくださいます。
そして、その光は、やがて来られる「真のパン」イエス・キリストを指し示しています。
ヨハネ6:35:「わたしがいのちのパンです。わたしのもとに来る者は決して飢えることがなく、わたしを信じる者はどんなときにも、決して渇くことがありません」
この箇所から、あなたも希望を見出すことができますように。
通読日:2025年11月8日 通読箇所:創世記18:1-15、士師記19-20章、マタイ14章
ブログ:聖書の名言集 執筆者:友喜
この記事が祝福となりますように。主イエスの御名によって。アーメン。
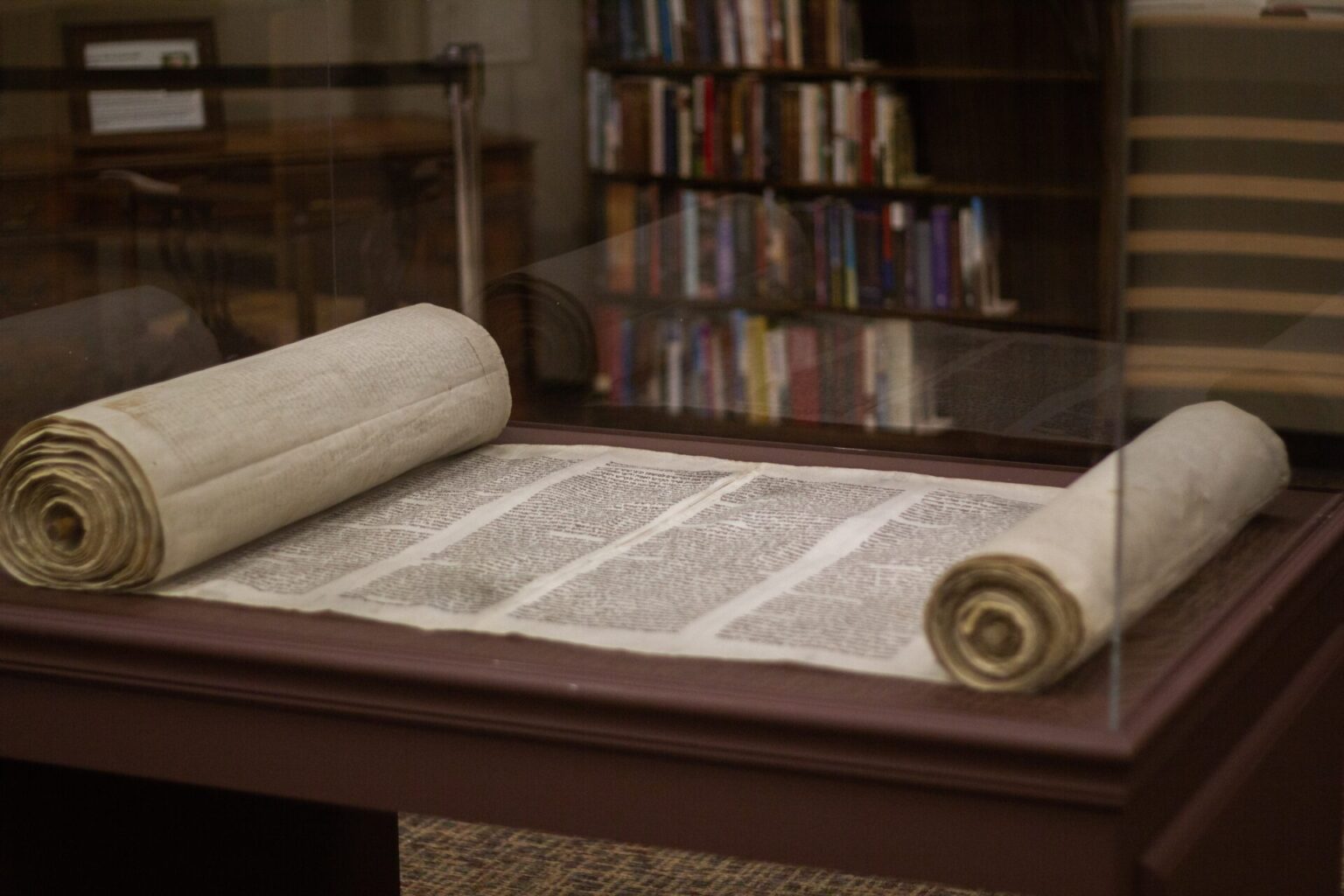


コメント